補聴器はできれば両耳で使いましょう。
補聴器は片耳で使うものと思っている人も多いようですが、左右の聞こえに差がないのであれば両耳装用が理想です。
補聴器を両耳に付ける利点

補聴器の両耳装用には主に6つの利点があります。
両耳装用の利点①どちらから話されても間こえる
補聴器を片方だけに装用している場合、つけていないほうから話されるとよく聞き取ることができません。つねに補聴器をつけているほうからばかり音があるわけではありません。
両耳装用の利点②方向感が得られる
方向感は片耳だけでも少しは得られるのですが、原則として、左右の耳に届くほんのわずかな音の大きさと時間差の違いを感知し、それを分析することで得られます。
音楽を聴くときにも音の立体感が得られます。
両耳装用の利点③言葉を理解しやすくする
人間の脳は両耳から音をよく間き取ったほう言語を処理しやすく、言葉の理解のためには片耳よりも両耳から音が聞こえたほうが有利です。
両耳装用の利点④聴力がアップする
両耳で聞こえると、脳で加算効果というものが働きます。片耳で聞くよりも小さな音でも聞き取ることが出来るということです。
会話レベルの大きさでは6デシべル程度聞こえが増すといわれています。
両耳装用の利点⑤カクテルパーティー効果
騒音のなかでも必要な音を聞き取ることができるカクテルパーティー効果というものがあります。
カクテルパーティー効果とは、パーティのようにまわりがうるさい場所でも特別な音、例えば自分の名を呼ばれた声や注意を向けている人の声は聞き取ることができる現象のことです。
これは、両耳に聞こえる音の違いを脳が分析し、判断することでこの効果が得られます。両耳に装用することでカクテルパーティー効果が得られ、まわりが騒がしくても特定の人の声が聞き取りやすくなります。
両耳装用の利点⑥間こえの劣化を防ぐ
耳に入った音は、脳でいくつかの神経を経過し初めて音として感じることができます。
ところが耳に十分な音が入ってこないと、この神経が劣化してしまい言葉の聞き取りが悪くなる場合があることが報告されています。再び補聴器で音を入れても回復しない場合もあります。
それを防ぐためにも片耳よりも両耳に音を入れていたほうがよいのです。
左右の耳で聴力に差がある場合は?

両耳の聴力の差が大きいと補聴器を使えないこともあります。
聴力に左右で大きな差があるときには、両耳に補聴器をつけることで、かえってバランスが悪くなって聞き取りにくくなつてしまうことがあります。
一般には左右の差が15デシベルから20デシベル程度までが両耳装用のよい適応と考えられていますが、それ以上であっても案外有用なことがありますので実際に試してみるとよいでしょう。
左右に聴力差がある場合
左右の耳に聴力差があり、片耳に補聴器をつける場合、個人の聴力によって付ける耳は変わります。
一概に述べるのは難しいのですが、一般に中等度の難聴の耳につけます。
つまり片方が軽度、もう一方が中等度の難聴の場合は悪いほうの耳につけて両耳効果が得られるようにします。片方が中等度でもう一方が高度の難聴の場合は、悪いほうの耳につけても限界がありますので良いほうの耳に付けるのが一般的です。
左右に聴力差はなく片耳装用の場合は?

左右に聴力差はなく、補聴器を片耳装用する場合は、基本的にどちらの耳でもかまいません。
ただし、いくつかの選択方法があります。
まず、利き手がどちらかということです。右利きの人の場合は右側につけるほうがたやすく装着できます。
ときに「聞き耳」というものがあり、聴力が同じでもなんとなく聞きやすい側というものがあります。普段電話を聞く側の耳のことが多いようです。
また、電話を聞くときに補聴器を通して聞くのか、それとも補聴器を利用しないでじかに聞くのかでも装用側は変わってきます。
軽度難聴の場合は補聴器を通さないで電話を聞くため反対側で、高度の難聴の場合には補聴器を通して電話を聞くようにするとよいと思います。
片耳だけが難聴の人に有効な補聴器
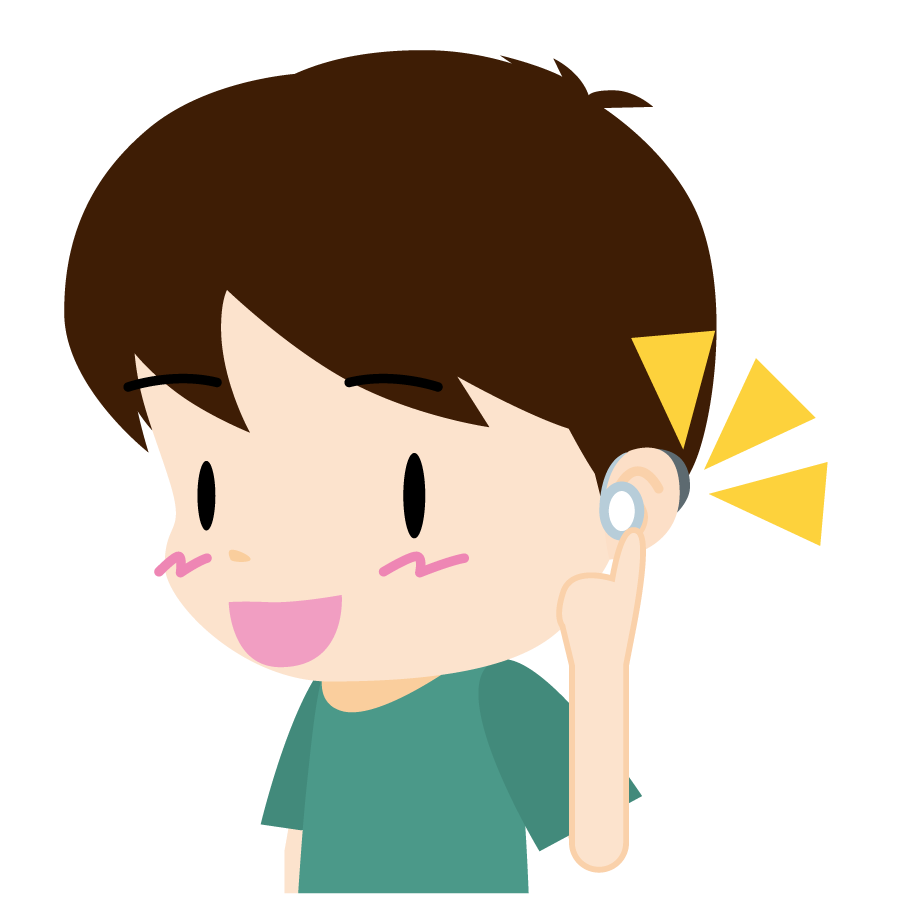
片耳だけが難聴の人に有効な補聴器もあります。
もし片耳がまったく聞こえなくても、もう一方の耳が比較的よく聞こえるときに有効なのがCROS(クロス)補聴器です。聞こえない耳に補聴器をつけても有効なきこえを得ることはできません。
こんなときに、聞こえない耳側からの音をよく聞こえる側の耳につけた補聴器に伝え、両方の音を間こえのよい耳で聞き取れるようにする方法です。つまリ、片耳で両側の音を聞き取れるようにするものです。
聞こえの悪い耳にはマイクだけが付いた補聴器をつけ、その音の信号をコードでつないだ反対側の補聴器に伝え音を出します。最近ではコードではなく無線で音を飛ばすものも出てきており、コードのわずらわしさも解消できます。
両側から話をされることが多い人にはとくに有効な方法です。
