�⒮�킨�����߂̑I�ѕ��I�����̎��ɍ������⒮���T����
�⒮��́A������Ȃǂ�d�C�I�ɑ������A��ɂ�钮�͂̒ቺ��₤�@��ł��B
�⒮������Ɋ��p���邱�Ƃɂ���āA�Ƒ��Ƃ̒c��y�����Ȃ�����A��̊����ɎQ���ł���悤�ɂȂ�����ƁA�ӗ~����̒�������߂����Ƃ��ł��܂��B
�����ł͂������߂̕⒮��̑I�т������Љ�܂��B
�������݂��o�����{���I��
![]()
�⒮��͌y�x�̓�̂�������g���n�߂�̂���������

�⒮�������̂͂��肬��܂ʼn䖝�����ق������̂��߂ɂ����̂ł́H�Ƃ�����������܂��B
�������A����Ȃ��⒮����g���Ă���̂łȂ���A��������⒮�����������Ƃ����Ď��������Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B
�⒮��ɂ�����炸����ɂ�钮�͂̕ω��͓����悤�Ɍ����܂��B�ނ���A������x�Ⴂ��������A�����ē����r�I�y�x�̂�������⒮������Ă���l�̂ق����A����ɂȂ����i��ł��悭��������X��������܂��B
�t�ɓ���i��ł��܂��Ă���⒮����g���n�߂Ă��A���܂��������Ȃ����Ƃ�����̂ł��B
����ɂ͔]���W���Ă��܂��B�����]�̉�H�͂˂Ɏh������Ă��Ȃ��Ƃ����������Ȃ��Ă����Ƃ������ۂ�����܂��B�ł�����A�\���ȉ����Ĕ]���h����������Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ł��B
�⒮��͂ǂꂭ�炢�̒��͂ɂȂ�����g���ׂ��H

�ŋ߂ł͌y�x�̓�ł��⒮�킪�g���Ă��܂��B
�{�l�������Ă��鍢��̓x������h���́A���͌����̒l�ƕK��������v���܂���B����ǂ��A������x�̖ڈ��͕K�v�ŁA���̊�{�ƂȂ�̂͂�͂蒮�͂ł��B
���̕\�́AWHO(���E�ی��@��)�̓�x���ނƁA�������Ă���Ή���ł��B
����Ō����41�f�V�׃��ȏ�̒����x��ƂȂ����Ƃ��ɕ⒮�킪�������߂���Ă��܂��B
�������AWHO�̊�͔�r�I�⒮�����ɓ���邱�Ƃ�����V�������܂߂����̂ł����A���ꂪ���\���ꂽ10�N�ȏ�O�̎�������⒮��͒������i�����Ă��܂��B
���\���悭�Ȃ����������A�y�x�̓�ł������b�g�������ł���悤�ɂȂ�܂����B
���݂ł́A���y�x�̓�A���邢�͍����悾���ቺ������ł��⒮��̓K���ƍl�����Ă��Ă��܂��B�������ɂ����č��邱�Ƃ������悤�ł�����⒮����l����̂��������߂ł��B
WHO�̓�x����
| ��̒��x | ���� | �����\�� | �⒮��͕K�v�H |
|---|---|---|---|
| ���� | 25�f�V�x���ȉ� | �����₫�����������A���퐶���Ɏx�Ⴊ�Ȃ� | �⒮��͕K�v�Ȃ� |
| �y�x� | 26�`40�f�V�x�� | 1m�̋����Řb�����������Ƃ��ł��A�������邱�Ƃ��ł��� | �⒮�킪�K�v�ȏꍇ������ |
| �����x� | 41�`60�f�V�x�� | 1m�̋����Řb�����傫�Ȑ����A�������邱�Ƃ��ł��� | �ʏ�͕⒮�킪��������� |
| ���x� | 61�`80�f�V�x�� | ���Ɍ������Ē���グ�����̂����炩�����Ƃ��ł��� | �⒮�킪�K�v�B�⒮����g��Ȃ��ꍇ�͓ǘb�A��b���K���ׂ� |
| �d�x� | 81�f�V�x���ȏ� | ����グ�����ł��������Ȃ� | ���Ƃ𗝉�����̂ɕ⒮�킪���ɗ��B���n�r�����K�v�B�ǘb���b��D�悷�ׂ��ꍇ������ |
�⒮��͌y�x�E�����x��҂ɂ���������

�⒮��́A���x��̐l�����ɂ͐g�̏�Q�ҕ����@��J�Ж@�Ŗ�������Ă��܂����A�⒮���K�v�Ƃ���l�́A���ۂɂ͂����Ƃ������邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B���x��҂������⒮���K�v�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�����x��ҁA������������グ�����������x�̓�҂̐��͂���߂đ����ł��B���̐l�����̑����͕⒮����g���Ă��܂���B���̒����x��҂̊w������̊w�K�͂����炭�s�\���ŁA�Љ�̑O�ʂɏo�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ނ��������A�܂��{�l��������ނ��낳����悤�ł��B�⒮��͂���璆���x��҂ɂ��K�v�ł����A�����̏ꍇ�A�g���Ă��܂���B�⒮��͎��ۂɖ��ɗ��̂ł����A������������Ȃ��Ƃ����S�����`���Ă���Ǝv���܂��B
��������́A����璆���x��̐l�����ɂ͋y���A�g�̏�Q�҂Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��̂ŁA�⒮��������ōw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����o�ϓI���R������܂��B
���{�ł͗�����̏ꍇ�A������70�f�V�x���ȏ�̓�̏ꍇ��g�̏�Q�҂ƋK�肵�Ă��܂��B����A�O���ɂ�40�f�V�׃��ȏ��g�̏�Q�҂ƔF�߂ĕی삷�鍑������܂��B
�������݂��o�����{���I��
![]()
��̕��������̓���
�����̕��̕��������͌l�l�ňႢ�܂����A��܂��Ɉȉ��̂悤��3�̓���������܂��B
1�ڂ͏����ȉ����������Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��B2�ڂ͑傫�ȉ��ɑ����R�͂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��B����́A�ӊO�Ɏv���邩������܂��A�����ȉ����������Ȃ��̂ɑ傫�����͋��A���Ȃ킿�������̕��������Ƃ������Ƃł��B3�ڂ́A������������Ă������Ƃ����蕷����������ł��Ȃ��Ȃ�i�ٕʔ\�̒ቺ�j���Ƃł����ɍ���҂̓�͌��t�ٕ̕ʔ\�̒ቺ���������Ƃ����Ă��܂��B
�����̓����ɑ��āA�⒮��ɂ͂ǂ̂悤�ȋ@�\������̂ł��傤���B�⒮��ɂ���Ă͒����̂��߂̂�������̃l�W�����Ă��܂����A��{�I�ȕ⒮��̋@�\�͎���3�ł��B
1�Ԗڂ́A���̑����ł��B����̓{�����[���Œ����ł��A���p�҂������Œ������܂��B2�Ԗڂ͉����̒����ŁA���͂ɂ���č�����������������Ⴂ����傫��������ł��܂��B�����̋@�\�͂�������u�����ȉ����������Ȃ��Ȃ�v�Ƃ��������̓����ɑΉ����Ă��܂��B3�Ԗڂ͑傫������̂�I����@�\(�o�͐����j�ł��B�����������⒮��ő��������̂͂悢�̂ł����A���Ƃ��Ƒ傫�ȉ����⒮��ł���ɑ�������ẮA�傫�ȉ������ȓ�҂͂��܂������̂ł͂���܂���B
���̂悤�ɒ������邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł����A�⒮��ɂ͉����Ԃ�������\�͂̒ቺ��₤�@�\�͂���܂���B���������āA�⒮��p��������Ƃ����āA�Ԃ���������100%��Ԃ�Ƃ������Ƃ͂�����Ɠ�����ł��B
�N����킸�⒮��̓K���͓����H

��ʓI�ɁA�⒮��͎Ⴂ�l�قnjy�x�̓�ł��g���X���ɂ���܂��B
�Ⴂ�l�قNJ����ȎЉ�������Ă��邽�ߕK�v�Ȃ̂ł����A����ɂȂ�ƕ������Ȃ��Ă��ς�ł��܂��Ƃ������Ƃ������A��r�I���x�̓�ɂȂ�Ȃ�����A�⒮����g�����Ƃ����ӗ~���킩�Ȃ�����̂悤�ł��B
����Ӗ��A���ꂾ���K�v�����Ⴂ�Ƃ������Ƃł��B�d�����o���o�����Ă���N��̐l�ł��ƕ��ς̒��͂�30�f�V�x�����炢�A����ɂȂ��Ă�����40�f�V�׃����炢����A������ɂȂ��Ă�50�f�V�x��������⒮��𗘗p���������߂��܂��B
�����������̂́A�⒮��������ɕ������ɂ������䖝�������Ȃ��ł������������Ƃ������Ƃł��B������x�ł��Ⴂ��������A�����Čy�x�̂�������⒮������Ă���l�̂ق����A����i�s���Ă����܂��g���������Ƃ��ł���X��������܂��B
�⒮��̑I�ѕ�4�̃|�C���g

�⒮��w���O�ɁA�ȉ���3�̃|�C���g�𒆐S�ɍl���邱�Ƃ��������߂��܂��B
�⒮��̑I�ѕ��|�C���g�@����ړI�Ɏg����
�ǂ�ȂƂ���ʼn���ړI�Ɏg�������̂����l���܂��傤�B
�⒮�������A�ǂ�ȂƂ���ł������ɕ�������悤�ɂȂ�悢�̂ł����A�Ȃ��Ȃ������͂����܂���B�����ŁA�⒮����g���ړI���ʂ��͂����肳���邱�Ƃ���ł��B
�Ⴆ�A�Ƒ��Ƃ̉�b����������悤�ɂȂ肽���̗͉�c�ł̐�������悤�ɂȂ肽���̂��A�d�b����������悤�ɂȂ肽���̂��A���邢�͍ł������Ă��邱�Ƃ͉����A�����Ă��̎��ɍ����Ă��邱�Ƃ͉��Ȃ̂����͂����肳���Ă����ƁA�⒮���I�т₷���Ȃ�܂��B
���R�Ɓu��������悤�ɂȂ肽���v�Ƃ������Ƃł́A�ǂ̂悤�ȕ⒮�킪�悢�̂��̌��ߎ�Ɍ����Ă��܂��܂��B
�⒮��̑I�ѕ��|�C���g�A�����悻�̗\�Z�͂����炩
�����悻�̗\�Z�����߂Ă������Ƃ��厖�ł��B
�ŏ��́A�⒮��̒l�i���ǂ̂��炢����̂��킩��Ȃ����̂ł��B�����̗\�Z�̖ڈ������炩���ߗ��ĂĂ����̂��������߂ł��B
�⒮��X�ɍs���ƍ����⒮����������߂���A���߂��邪�܂܂ɍl���Ă����\�Z����⒮����w�����Ă��܂���������܂���B�������A���̕������ɖ{���ɖ𗧂��̂Ȃ�A�����\�Z���I�[�o�[���邱�Ƃ���ނ����Ȃ��ł��悤�B�������A�ŏ��̍l���Ƃ��܂�ɂ������ꂽ���i�̏ꍇ�ɂ́A������x��ÂɂȂ��Ă݂܂��傤�B
�����ɂƂ��ĕ��������悭�Ȃ邱�Ƃ́A�����炮�炢�̉��l������̂��B�����āA���̉��l�̕������̐��\������̂����l���Ă݂܂��傤�B
�⒮��̑I�ѕ��|�C���g�B�����悻�̗\�Z�͂����炩
�⒮���I�ԍۂɂ͎����ő���ł��邩�ǂ����Ƃ����̂��d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��C�����\����c�}�~���������ȂǁA���ɍ���҂ɂƂ��Ă͈����ɂ����ʂ��⒮��ɂ͂���܂��B
�܂��A�a�C���̊W�ł����g�ł͑��p�E���삪����ȏꍇ�ɂ́A�Ƒ����삷��l����삵�₷�����̂�I�Ԃ��Ƃ��厖�ł��B
�����ŕ⒮������ɑ����ł��邩�A�X�C�b�`����ꂽ�������ł��邩�A�{�����[���傫�������菬����������ł��邩�Ȃǂ��m�F���邱�Ƃ��������߂��܂��B
�⒮��̑I�ѕ��|�C���g�C������ԕi���\��
������ԕi���\���m�F���邱�Ƃ���ł��B
�̔��X�ɂ����܂����A�⒮���������x�̊��ԑ݂��o���āA���ۂɎg���ł����ɗ����ǂ������������Ă����ꍇ������܂��B
��ʓI�ɃI�[�_�[���C�h�̎����Ȍ^�⒮��ł͍���Ă݂Ȃ��ƌ��ʂ��m�F�ł��Ȃ��Ƃ��낪����A���̊��ԓ��ł���Εԕi�ɉ����Ă����ꍇ�������Ǝv���܂��B
�������^�⒮��ł��ŋ߂͗L���E�����Ŏ����p�⒮���݂��Ă���邱�Ƃ�����܂��B�̔��X�ɂ���ď������V�X�e�����قȂ��Ă��܂��̂ŁA�悭�m�F�����ėL���ɗ��p���Ă��������B
�ŋ߂̓C���^�[�l�b�g�ł̔̔��ł������V�X�e����ԕi���\�Ȕ̔��X������܂��B�C���^�[�l�b�g�ł̍w�����͕K���������邱�Ƃ��������߂��܂��B
�������݂��o�����{���I��
![]()
�⒮��͍�����Ηǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ�
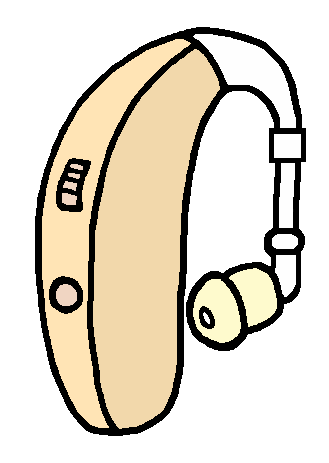
�⒮��͍�������ꂾ�������₷���Ȃ�Ƃ����킯�ł͂���܂���B
�⒮��̃J�^���O������ƁA�܂����̉��i�Ƀr�b�N�����Ă��܂��܂��B�������̂𗼎��ɔ����ƁA�y�����ԕ��݂ɂȂ��Ă��܂����̂�����܂��B
�l�i�������Ȃ�Ɗm���ɂ悢�ʂ������̂ł����A�K�������l�i�ɔ�Ⴕ�Ă��ꂾ���Ԃ��₷���Ȃ�Ƃ������̂ł͂���܂���B�t�ɁA�ቿ�i�̂��͖̂��ɗ����Ȃ����Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�����Ă��\�����ɍ����ꍇ������܂��B
�܂��A�Ў��ɍ����⒮���������A�����Ɉ������̂������ق��������₷���ꍇ������܂��B����ɁA���i�قƂ�ǎg��Ȃ��@�\�̂��߂ɉ��i�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B
�ŋ߂̕⒮��͑����ɂ悭�Ȃ��Ă��Ă��邽�߁A��r�I�ቿ�i�Ȃ��̂ł��\���ȋ@�\�������܂��B
��O�Ԃ������Ԃ��ꏊ���ړ�����Ƃ����@�\�ł͓����Ȃ̂ł����A���̎��Ɖ��i�̈Ⴂ���ǂ������邩�́A�l�̉��l�ςɂ���ĕς��܂��B���l�ɕ⒮��̉��i�̕]�����A�o�ϗ́A�l�����A�������̈Ⴂ�ŕς���Ă��܂��B
�����A�⒮��͌����Ƃ��Ė��������Ԏg���܂�����A�䖝���Ȃ���g���̂͂ǂ����Ǝv���܂��B�ق�̂킸���̕s���������Ԃɒ~�ς��āA�������茙�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�ނ�݂ɍ������̂��K�v�͂���܂��A�����̐����̎��ɂ������܂��̂ŁA�\���������āA�[���������̂��w�����邱�Ƃ��������߂��܂��B
�⒮��́A����������K���Ă���Ƃ͌���܂��A�傫�ȉ����o�邩�琫�\�̗ǂ��⒮��A�N������^���Ă������߂��Ă�������ǂ��⒮��Ƃ����킯�ł�����܂���B���p����{�l�̒��͂ɍ��������̂�I�ԕK�v������܂��B
�⒮���W����̑I�ѕ�

�ʐM�̔��̍L���Ȃǂ����Ă���ƁA�u�W����v�ƕ\���������̂Ɓu�⒮��v�Ə��������̂�����̂ɋC�����܂��B
�⒮��͈�Ë@��Ƃ��Ă̏��F�����́A�W����͓��Ă��Ȃ��Ƃ������������ł��܂��B��Ë@��̏��F�邽�߂͂��܂��܂ȃf�[�^���o����ȂLjĊO��ςł��B�W����̏ꍇ�͂���������ɉ����@��Ƃ��Ĕ̔��ł��邽�߂ɕ⒮��Ƃ������̂��g���Ă��܂���B
���\����S���ɖ�肪������̂����ɂ͂���̂�����ł��B�ʐM�̔�����Ă���⒮���W����́A���̂قƂ�ǂ��y�x���璆�x��җp�ł��B
�������A�����̏��i���w�����Ďg���Ă݂����̂̌��ʂ�����ꂸ�A���̂��ƂŁu���̕⒮��E�W����̓_�����v�A�u���Ɍo���Ȃ��v�Ȃǂǂ��������ă_�����Ɣ��f���Ă��܂����Ƃ͔��������Ƃ���ł��B����́A�l�̊��z�ł��萳�����]���Ƃ͂����Ȃ����̂ł��B
��ł��q�ׂ��悤�ɁA�⒮���W�����͑��l���ǂ��������A�������g�ɍ������ǂ������S�Ă�����ł��B
�o���邱�ƂȂ�A�F�X�ȕ⒮��������Ď����̎��ɍ��������̂�T���Ƃ����I�ѕ����������߂��܂��B
���������߁I�����݂��o�����{����
![]()
